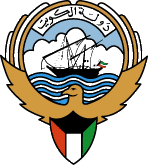クウェート独立50周年を心よりお祝い申し上げます。
クウェートの国章には預言者ムハンマドの出自クライシュ族のシンボル、金色のハヤブサの翼の上に海洋に浮かぶダウ(Dhow)船が描かれています。
アラビア半島の東側付け根に位置するクウェートはインド、ペルシャ(現在のイラン)からアラビア半島に下る中継地として、また湾岸地域からイラクのバスラ、バクダットへと向かう途上に位置する陸上交通の要所でした。同時にアラビア諸港、ペルシャとの沿岸貿易港として知られていました。
クウェートが都市国家の体裁を整えた1752年以来、クウェート人の主要な経済活動は海に依存した漁業、天然真珠取り、さらにアラビア沿岸諸国間の海洋交易として発展します。ダウ船と呼ばれるクウェート独特の帆船は、製造技術はインドから伝わったとされていますが、クウェート人の独創的技術により改良され、多くの種類のダウ船が誕生しました。
1900年代より沿岸貿易木造帆船としてダウ船は発展し、遠くインド、東アフリカにまで航海し、海洋貿易の主役となりました。1940年頃には200トン級のダウ船が150隻もクウェート湾を賑わせていました。
しかし石油の発見により、大活躍したダウ船の船員も船長も石油関連の会社に就職し、船を動かす人がいなくなってしまいました。
写真にあるダウ船ファティルカー(Fateh-el-Khair)は、1952年バスラのペルシャ人船長に売り渡され、ダウ船を中心とする海洋貿易の時代は終わりを告げました。
1994年クウェート大学教授ハッジ(Hijji)博士は探していたファティルカーを発見しました。クウェート科学振興財団(KFAS)は直ちに買戻しを決定し、修復工事を行いました。復元されたファティルカーは2000年に完成したクウェートの科学センター(The Scientific Center Kuwait)に展示されています。
一旦は他国へ売られてしまったものを買い戻してまで復元した理由は、クウェートの「海洋民族としての誇りと伝統を未来に残す」という気持ちの強い現れです。船名ファティルカーとは「幸運の始まり」の意だそうです。
クウェートは湾岸諸国の中で最も進取の気性に富んでいるといわれています。かといって歴史と伝統を疎かにしているわけではないことが、そのことからも伺い知れます。3000年紀の出帆にあたりクウェート首長は「クウェートを金融と世界貿易のセンターにする」という目標を掲げ、巨額の開発計画を採択しました。
広大な砂漠をラクダに乗って移動する民族にとって、行くべき方向の道しるべとして星を頼りとしてきたと思われます。そこで培われた時代を予見する慧眼は、海を目指して移動し、定着してクウェート国を築き上げました。クウェートが掲げた新たな目標は、原点回帰に基づく目標のようにも感じられます。
日本も現在にわかに海洋国家としての開国の歴史が回顧され、新時代に対応する海洋国家像が模索されています。
クウェートと日本の、過去に増したる新たな絆が結ばれることを心より祈念いたします。